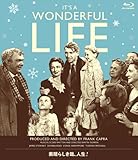黒澤明「生きる」(1952)ゴンドラの唄という個人卒業式、星の視点で描かれる生死一体。

黒澤明監督の「生きる」(1952)を観た。名作として名高く、ゴンドラの唄のシーンが、映画の象徴として語り継がれている傑作である。ベルリン市政府特別賞を受賞し、数々の映画ランキングに顔を出してきた。それらの事実は、この映画が、普遍的なものを描いている、という感想を多くの人が抱いたことに拠っている。トルストイを原作としているが、あまりにも黒澤明映画であり、志村喬を主人公、あるいはメインとした黒澤映画の中では、ひとつの達成点となっている。多くの芸術家の例にもれず、全ての作品がつながっており、心の動きと言うと浅すぎて、魂の流れと言いたいものが通底していて、この映画ひとつで、その背景まで押し寄せてくるかのようだ。「酔いどれ天使」(1948)「醜聞スキャンダル」(1950)「生きる」(1952)と志村喬が主人公級で描かれた作品の流れの中で、ひとつの完結編と言いたい気持ちがするのは、わたしだけではないだろう。
目次
- 「生きる」までの流れ、フランクキャプラ「素晴らしき哉人生」の影響、星の視点
- 生と死は一体のものである為、死に接近することで生に目覚めていく
- 社会の慣習の中で「生きる」ことを決意する男、ゴンドラの唄という卒業式
- 生命の奇跡、変化という永遠の中で
- 黒澤明「生きる」動画
- DVD紹介、関連作品、書籍
1「生きる」までの流れ、フランクキャプラ「素晴らしき哉人生」の影響、星の視点
「生きる」までの流れだが、「酔いどれ天使」では、志村喬は、アルコールを手放せない型破りな医者であった。作品の中心に据えられた泥池を前に、「何もかもがばかばかしくてヘドが出そうです」というセリフを言ったのは、彼だったか、それとも、死んだやくざを慕った女の方だったか。結核で死ぬ者、そして生き残る女の子、生命を燃やしぶつかり合う二人の男、医師とやくざ、志村喬と三船敏郎。生きる、ということ。生命の輝きが、荒々しくも美しく描かれて、それらは、映画の前のわたしたちに処方される薬なのだった。「醜聞スキャンダル」では、人間の弱さから道を外れてきた志村喬扮する弁護士が、最後になって、自らの真実を語るところまで、己を高めるのだった。そのきっかけとなるのは、病気に伏せていた純粋な娘の死であった。その死が、彼を生きることに目覚めさせるのであった。「明日からこそは、来年からこそは」と口にし、その通りにならない、わたしたちの兄弟であり人間の弱さを代表した男は、泥池に星を見出し、真実を生きようとする。そのとき、三船敏郎扮する画家は、「今日、星が生まれた」と言う。ほぼ同様の構造を持ち、クリスマスの場面など影響が強く窺える、フランクキャプラの「素晴らしき哉人生」では、翼のない天使に、ついに翼が生えるのであった。日本の黒澤明の作品では、星になるのである。川面に映る銀河に生死を見て取る宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を思い起こさせて楽しく、泥池に咲く蓮の花のイメージは、「姿三四郎」(1943)で描かれ、それが東洋の伝統に根差したイメージであることは言うまでもない。「生きる」では、主人公が目覚めたとき、女学生が歌う「ハッピーバスデートゥーユー」が響くのであった。星が生まれるのである。影響が濃い「素晴らしき哉人生」では、主人公は、事業の危機を前に、クリスマスにも関わらず、絶望し、自殺すら考えているのであった。そして、この死への接近が、人間が生きていること、存在していることの奇跡を、主人公に体感させる出来事へと導いていく。そこには、歌があり、人々の喜びがある、生きるということはどういうことなのか、星の視点から描かれる。それどころか、冒頭からして星が人間の世の中を見守っている場面から始まるのであった。死んでからお星さまになる、と古来の人々は言った。それは本当なのだった。はじめは、幼心に信じて、大人になるにつれて、死んだら死んだだけと石化していき、やがて、万物とは、その原子は、開放されて、あたらしい形となって生まれ変わるのを繰り返しており、色即是空、空即是色、無極にして太極、無は全てを生む根源であり、万有であり、人間の目には見えないが存在するとしか言いようのない生命の流転に目が開かれ、星のめぐりによって証明され、生命の神秘に導かれていく。意識発展のための、古来からの智慧、イニシエーションの儀式は、近代化と共に失われ、わたしたちが、新たな段階に足を踏み入れるためには、何らかの決定的な出来事を待たねばならないのであった。「生きる」の主人公にとって、それは、胃がんという病気なのであった。「この主人公は生きていない。この男がそのことを更に自覚し、考えを改めるには、更に彼の胃が悪くなる必要があるのであった」というナレーションは、このような認識によるものだと言えよう。主人公は、病気によって、死に直面することによって、生きることに目覚める。そして、主人公を説明するこのナレーションは、誰なのか。この高い視点は、「素晴らしき哉人生」で言えば、星なのであった。「生きる」は、「素晴らしき哉人生」の変奏なのであった。多くの芸術家が繰り返し描いているのは、この青い星の上に立ち、他の星を見上げるわたしたちと、星となったものたちからの柔らかい視線なのである。真に生きることによって、自然と到達する境地なのだろう。
生と死は一体のものである為、死に接近することで生に目覚めていく
火葬場が近所に建設されることに反対する運動のことを聞いたことがある。なぜなのか、死を遠ざけたいためであろう。人は、生まれると共に、死ぬことを約束される。更に言えば、生まれるとは、移行することでもある。母親の胎内に生命が宿る。それはどこから来たのであろうか、それは何万年を旅してきた生命である。それが、母親の胎内に宿り、そこを世界とする。しかし、その世界を出なければならない、温かく快適な子宮という世界から死ぬこと、これが生まれることなのであった。断末魔の叫び声と共に、人は、このような世界に生まれ落ちる。ひきこもりの子供たちを考えてみよう。彼らは、幼年時代という子宮の中から出ることが怖いのである。それもそのはずである、そこから出ることは、死んで生まれ変わることである。誰もが死を恐れる。そこには適切な橋渡しがなければならない。社会が失ったのはそのような智慧であり、日常に存在する死への感覚である。わたしたちは、母親の膝元から、小学校、中学校、高校と移行を繰り返し、卒業と入学を体験していく。これらは、生と死の体験である。そして、このような生と死を潜り抜けること、更には万物の生死というものが語るのは、変化こそが永遠であり、わたしたちは、行きて行きて行く者なのだ、という認識である。どこかの段階で固定が始まると、その者は頑固になり、しがみつき、後ろを振り返って石化してしまう。もう一度、自分を壊して、死に、新しく生まれ変わること、これがチャレンジになってくる。どのような人間も、この生死のあらゆる段階にいる。そして、死がなければ、生もまたないのである。なぜなら、生と死は一体のものであり、わたしたちは、合理思考を手にしたときから、物を二つに分けるように訓練する。光と影、男と女、YESとNO、天と地、右と左、生と死、それらは、相対する二つの組み合わせであり、これが、人間に矛盾と葛藤という分裂を負わせる。この二元を超えること、これがシャカが到達した智慧に他ならない。重要なのは、わたしたちが二つに分けたのであって、この星が、二つに分かれているのではない。わたしたちが、分けたのである。世界が分かれているのではない、ということである。生と死は、言葉遊びでもなんでもなく、一体なのである。人間が変化し続けるということは、この星の法則に適っており、それは、生と死の円環を繰り返すことである。そうして、大いなる円環の中でもまた、事実はそうなのである。その認識を欠き、何かにしがみついたときに、水は生まれ変わる機会を失い、腐っていくのである。変化し続けるものは、この星に適っている。自然法則に適っている。これを自然法爾と親鸞は言った。この人間として生まれ落ちた中でも、何度も生まれ変わり、成長を続けていく者がいる。それは、生死を超えてきた者である。移行を繰り返してきた者である。成長とは、変化と同義だと知る者である。古い自分を壊して、新しく生まれ変わり、意識が拡大し、発展し、同じところに留まっていない。そうして、固定する者との差が開いていく。固定する者は、全てを知っていると思い込み、それにしがみつくだろう。自分が知らないことが存在するということは、自分を揺るがすことだ。自分を揺るがす危険を避けて生きるだろう。そのために、目がくもり始め、全てが自分の知っていることで構成されていると思い込むだろう。事実としては、全てを知ることは人間には不可能であり、何も恥ずかしくない真実であるにも関わらず、素直な目が失われて、我見にこだわり、自らを守り、古い自分にしがみつくだろう。それは、生きないことである。そうして、生きている者を目にすると、狂わんばかりの憤怒と嫉妬に見舞われるだろう。なぜなら、生きていない者にとって、生きることは、喉から手が出るほどに欲しいものであるから。それが許せないのである。映画「生きる」で、主人公が死を意識して、仕事の中に生きようとしたとき、市役所の公務員たちは、主人公を煙たがる。当然である、何もしないことこそ、誰にも批判されずにいる方法であり、それらを徹底することこそ、問題を起こさずに運営するという市役所の伝統方針なのであり、今日でもその通りである。それは、善悪を超えて、社会的慣習となり多くの人が認める事実である。主人公は、慣習の中にあって、生きようとする。それは、変人に見えるような、人間同士の空気などに絡めとられない、星の視点に目覚めた男の行動であろう。
社会の慣習の中で「生きる」ことを決意する男、ゴンドラの唄という卒業式
主人公は、良くも悪くもなく、ただ社会の慣習の中で、良かれと思って、仕事をするふりにも励み、その何事も問題が起きない長い30年の職業人生を営んできた。しかし、己に与えられた生命を生きてきた、とは言えない。近づく死によって、主人公は、その現実に向き合う。はじめて、そこに曇りなき目が開かれる。彼は、若い女の子の躍動する生命に惹かれる。一体どうすれば、自分も、そのように、真に生きることが出来るのか。何かを作ること、何かを生むこと、女の子をきっかけに、男は目覚める。創造するハタラキ、これこそが、命のハタラキであることに、男は直観的に気付く。そうして、このときに、主人公は一度死んだのである。同じ店に集まっていた女学生たちは、誕生日パーティをしている。そして、「ハッピーバースデイ」の歌が響く。男は、死んで、生まれ変わったのである。この生死を体験したときから、肉体の死は、彼にとって恐れるものではない。生死の移行をこのときに彼は体験したのだから。男は、前のめりに、生に向かっていく。ゆきて、ゆきて、ゆく者になるのである。この女学生の誕生日会と彼が星として生まれたときが、重ねられていることに対して、あまりにも偶然が行き過ぎていると合理的に考えてしまう者もいるかもしれないが、より高いリアルが描かれている、と考えるのが良いと思う。なぜなら、視れば視るほどに、あらゆる物と事が、全ての生命の構造と不思議を代表してそこで待っているようなものなのだから。ヘミングウェイの短編に「何を見ても何かを思い出す」というタイトルのものがあったと思う。仏教的世界観では、縁起と呼んできた。老子はこう言っている。「常に無欲、以てその妙を観る。常に有欲、以てその徼を観る」それが蛹として死んで、蝶として生まれるイメージでも良かったし、木から落ちたセミが鴉の胃袋に収まる絵でも良かった。それどころか、わたしたちが、植物や動物の死骸を口にして、わたしたちのなかに生きる、という飲食自体でもそれは示されている。生まれ変わった主人公は、小さな公園の設立に邁進する。それは、なんでも良かった。彼の生命の前にあり、その命を燃やせるものであれば良かった。彼は、充実を手にする。生きている喜びを手にする。命を燃やさずに、ただ長引かせ、生きてこなかった、通帳にお金を貯める生活では得られなかったものが、彼の手の中に収まる。死の直前になって、彼は目覚めたのである。自分の命を何に使うかを定め、それに邁進したときに、初めて生命は輝き、生きていると言えるのだと。彼は困難と思われる役所の機構の中で、何も恐れずに物事を行っていく。そして、ブランコに乗って、「ゴンドラの唄」を歌う。そこには、楽しい響きさえある。この先、自分は死ぬだろう、というのは、誰でもそうなのである。しかし、ブランコに乗っている現在、彼は生きているのである。素晴らしきかな、人生なのである。彼はたった一人で卒業式をしているのだ。次の入学は、魂の次元であろう。黒澤明映画「夢」で、最後に出てくる老人が、よく生きた上での死は、喜ぶべきお祝いだとして、村でお祝いの儀式をしているシーンがある。ユングは、肉親の死を体験したとき、死は、永遠との結婚である、との認識を深めた。そして、「死は終わりではない」との言葉を遺した。空海は、「うまれうまれうまれうまれてはじめにくらく、しにしにしにしんでしのおわりにくらし」と言っている。
生命の奇跡、変化という永遠の中で
生活の中で、締め切りというものがある。それがあることで、物事に生命が走ることもよくある。締め切りとは死である。そして、その期限までに、何とかこなそうと、わたしたちは生きる。死を前提としたときに、生は死と一体となり、輝き出す。安全とは、時に、生きないことである。生きることは、リスクを伴う。危険の中で、生命は花開く。危険なものを全てこの世から消そうということは間違いのもとである。生きる以上、危険と死と隣り合わせであり、だからこそ、ブランコに揺れて歌う時間に輝きが現れる。生きない世界を徹底すれば安全に思えるが、それは自然に反するために、いつかダムは崩壊し、どこかで生命は暴発してしまうだろう。それは、個人の問題であると共に、わたしたちの問題である。彼のところにそれが噴き出して、ちょうど生贄のようにそれをスケープゴートに、わたしたちはますます生きない安全の中に逃げ込んでいく、としたら、死を否定するのならば、わたしたちは半分になり、いつかそれは、危険水域に達し、決壊して、最大のレベルで襲ってくるだろう。「宗教っぽい」という言説は、死を意識したくない、ということの現れである。宗教とは、死を前提としている。かつて、日本の山には、死者が棲んでいると考えられていた。天皇たちは、熊野の山に登った。山は命を産み、荒々しく奪う。死に、そして生まれ変わる生命の奇跡に触れることで、わたしたちは全体を体感するだろう。上半身しか洗ったことのない者が、下半身を初めて洗って、ようやく自らの全体を知るだろう。自分が死なないとでも思っていたかのように、半分以上のことに、わたしは目を伏せてきたのだと。「生きる」の主人公を笑うことなどできない、わたしだってそうなのだ、と。そして、いきていきていくものになろう、と決意するのだ。