「深夜公園の音楽会」(2008)
2016/07/09
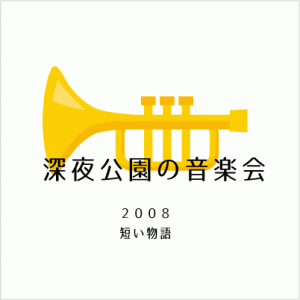
深夜十二時。男はギターを背負い、アパートの近くの公園まで歩いて行った。
公園に入ると、砂場の近く、コンクリートの段に三人の若い男女が腰掛けて何かを笑っているのが見えた。彼は、足音に注意を向け、奥の高台になったところにあるベンチに向かう。オレンジ色の外灯が薄い光を辺りに投げかけてはいたが、はっきりと目に見えるものはなかった。夢の中で見るイメージに似ていた。そのせいで、常日頃、自分の目に見えるものが全てイメージであるということが、はっきりと身体的に感じ取れた気がするのだった。
ベンチに腰掛けると、ケースからギターとノートを取り出し、ジーンズの前ポケットに手を突っ込んでピックを握り、その手を夜の中に戻す。足元にノートを投げて、ギターを身体で抱える。頭上を見上げると少し欠けた月が薄い雲を照らしていた。
二曲演った。ギターの音色と歌声が途切れ、自動車の走り去る音が聞こえ、足元のノートが風でめくれあがった。歌う前と後で世界は何も変化しない。そのことを確認すると彼は次の曲を探す。次の曲、というのは厳密には楽曲を意味する訳ではなかった。それは、彼の皮膚にある感覚に出口を与える器のことであり、原初の雄叫び、言い尽くせぬ言語だった。歌と音で空中に創り出す、自由な乗り物。どこでもないし、どこにでもいけるがどこにもいかない。彼の昼間の活動に比べると、それは奇跡的な場所だった。「音楽」にさえ縛られていなかった。そういう意味では全くの徒労、無意味なことだと言う者もいた。彼を笑う人達はたいてい、音楽を演っているといえば、レコードデビューして有名になって紅白歌合戦に出て、アンプの上に足を乗せて長髪を振り乱すというような夢を追っている人だと思い込んでいた。音楽は万人に開かれている。そこには原初的な喜びがあった。いくら年をとり、浮世に飽こうとも、手足が不自由になろうとも、音楽の喜びと自由はいつでも風のように自分を包むだろう、社会とは一切の関係なく、他人の評価とも無縁に、魂を包む、変幻自在な美しい衣として。
彼はギターを抱えて、辺りを見回す。風と闇が心地よく頬を撫でた。公園という規定が剥がれて、彼の前でその場所は名を失い、広い部屋のように身体を包み始めていた。内面が外面の世界に投射され、自然と一体化し、どこまでも広がり、月明かりに融合していく。
公園で歌いはじめて、初めての観客は緑色をしたバッタだった。バッタはいつの間にかノートの端に忍び寄り、いつまでもそこにいた。一度はノートに詩を書き付ける邪魔なので、軽くつまんで階段に向かって放り投げた。それでもバッタはまたやってきて、ノートの上に細い足で立ち尽くしていた。彼がその時のことを思い返して微笑み、胸の中を眺めていた時に、若い男が眼前に現れた。
「すいません、あの僕、ピザ屋でバイトしているんですけど。これ良かったら食べてください」
五メートルも離れたところで、男は言い、おずおずと頭を下げながらやってきた。黒色のTシャツにジーンズをはいている。頭頂部から髪を前に垂らしていた。
「なんですかそれ」と彼は訊いた。
「オリエンタルサラダです」と若い男は言った。ケーキを入れるような箱に入った大掛かりなものだった。
「いいんですか?」
「どうぞ。いい歌を聞かせてもらったので」
「どうもありがとう」サラダを受け取り、ベンチに置いた時に、笑いながら二人の女がやってきた。片手にそれぞれ缶ビールを手にしていた。
背の高い女が笑って、男の頭を叩いた。彼女は鎖骨がはっきり見えるくらいに胸元が開いたカットソーを着ていた。胸の谷間が目立った。髪は後ろで束ねられている。もう一人の女は小柄で、長い髪を真ん中から分け、前髪は顔の輪郭に沿って撫で付けてあった。黄色のスカーフを首に巻いて垂らしていて、あまりに大きい胸を隠しているように見えた。無意味に肩を叩き合い、笑い合う、酔っ払いの時間が突然に彼の目の前に広がった。それから、彼女達はビールを買ってくるので一緒に飲もうと言い、コンビニに駆けて行った。
残された男としばらく話した。バンドでギターを弾いているのだと若い男は自己紹介した。出身地が近かったので、二人とも頬が緩んだ。
「可愛い女の子が一緒でうらやましいよ」
「一人は彼女で、もう一人はその友達なんです」と若い男は言った。「僕、トモっていいます」
「シンヤだよ」と彼も名乗った。
トモはピザ屋のバイトが終わった後に、公園で彼女達と落ち合い、酒を飲んでいたのだと話した。バンドはスカというかパンクというか、そういうのです、となぜか恥ずかしそうに言った。トモは二十三歳だった。
女達が戻ってきて、足元のノートの前に缶ビールとお菓子を並べた。くまさんビスケット、ロケットチョコ、うまい棒、よっちゃんイカ。三人は地面にあぐらをかいた。
「のみましょう、おごりですよ」と背の高い女が言った。これがトモの彼女だった。元気で最も口が軽く、三人の冗談と真面目な語りの流れを指揮しているのは彼女だった。小柄なスカーフの女は、落ち着いていて、控えめだったが、最も知性的で好奇心に光る目をしていた。
「どうしてこんなところで歌っているんですか?」とスカーフの彼女は訊いた。
シンヤにはうまく答えられなかった。
トモの彼女が駅前で弾き語るのをすすめ、大阪にはチャンスが転がっているし、私達のバンドもメジャー契約寸前というところまで来ているのだと話した。彼女はトモと同じバンドのベースをしていた。
「なんか空が似合う人ですね」とスカーフの女が言った。「青空が」
「今は夜空だけど」とシンヤは言った。
スカーフの女は笑った。「でも本当に透き通る声で、いつまでも聞いていたいと思ったんですよ。なんていうか、心にくるっていうか。お世辞じゃなくて。だからこうして来たんです」と彼女は言った。
シンヤは彼女と目を合わせていると心地良かった。
「なんか目線がいい」と彼女は言った。「なんか安定感がある」
うまく言えないけど、心の表現て感じですね。別に気にいられるためにやる必要はないと思います。なんというかドシロウトが言うのはおこまがしいかもしれないけど、間違った、おこがましいかもしれないけど、あれ、おこが?おこま?とにかく、良かったです。
二人はしばらく表現について語った。それから、トモのバンドの話となり、女達が同じ病院の看護士仲間だという話になった。もうそこは夜ではなかった。黒い包装紙で窓を塞いだ昼のように、人の為す事が主役でしかない仮の夜だった。それでも、表面や思惑や誤解がどうあれ、あのバッタと同じなんだとシンヤは思った。そういう生き物の習性が可愛いとシンヤは思った。スカーフの女の隠そうとしている大きな胸や、どちらかと言えば見せたいという胸の谷間や、彼女に支配されている若いギター弾きのおとなしさや、バッタに歌を聞かせる男の。
「一曲やってくださいよ」とトモが言った。
「いいけど、ちょっと近すぎるな」とシンヤは言った。「恥ずかしいよ」
シンヤの足元のノートを囲むように、三人はあぐらをかいていた。
「じゃあ目を閉じているから」とスカーフの女が言って笑った。
「キスしたくなるからだめだよ」
「えー」とスカーフの女は言って、目をぎゅっとつぶった。
「うそうそ、冗談だよ」とシンヤは言った。
トモの彼女が、私の友達を口説いているんじゃないでしょうね?というように、急に真顔になって様子を窺うようにした。大きな葉っぱの隙間からのぞいているような表情をしていたが、そこには葉っぱがないので、滑稽な感じがした。
「じゃあ歌うよ、やっぱり目を閉じて」
三人は目を閉じた。シンヤはEマイナーを一度かき鳴らす。静かに腰を上げて、ギターを抱えたまま床にしゃがみ、スカーフの女の唇に優しくキスをした。次にトモの彼女に、最後にトモにキスをした。
「うわー」とトモは言って、唇を押さえた。
女達は何も言わなかった。目が外灯に照らされて奥深く光っていただけだった。
トモがギターを弾き、三人で「スタンド・バイ・ミー」を歌い、通りかかりの猫とバッタを加えて、皆でスピッツを何曲か歌った後、シンヤは別れの挨拶をした。「またどこかで」
「深夜の公園で」
「どこでもない場所で」
「三百年後に」
「もっとよ。三千年後に音楽会を開きましょうよ」
(2008)
