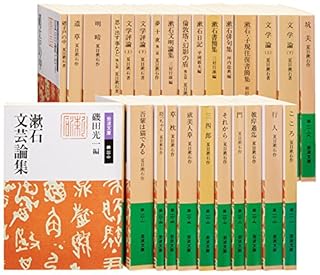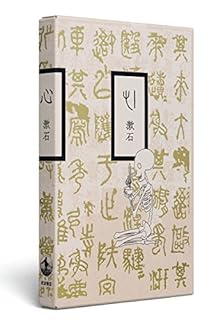夏目漱石「こころ」(1914)
2016/07/09
夏目漱石の「こころ」を久しぶりに読了した。「こころ」は原稿用紙換算、およそ五百枚、三つのパートに分かれている。「先生と私」「両親と私」「先生と遺書」夏目漱石の「こころ」は、文体がいい。久しぶりに読んでみて、これは文体が全てと言ってもいい気がしている。この小説を四ヶ月弱で、新聞に連載したというのが、信じられない。ある一文の後に、一文が浮かびあがり、またそれによって一文が続く。というのを、リズミカルに繰り返していく、夏目漱石のこの文体が、ページをめくらせる力になっている。夏目漱石のような、書く本人も、書きながら、ぐんぐん前に進んでいく小説というのは、いい。かっちりしているけど、文章の流れが死んでいる小説よりも、こちらの方がいい。たぶん、文章の流れは、即興的な、生命のリズムになるから、その生命感に読者が包まれるのだな。だいたい、こういうことを書こう、と決めるけれど、あとは書いている文章の流れで進めている、という感じがいい。
ただ、先日再読した「坊っちゃん」のほうが、生命感とリズムが、より気持ちいい、とは思う。「こころ」においては、「先生と私」の、先生に過去があるらしくて、それを先生が会話なりなんなりで仄めかしていき、「私」が先生に興味を抱いて、問いただすも、答えは得られない、という流れが、鼻にはつく。ただ、文体はいいので、内容はそこまで気にならない。「両親と私」は、「私」が実家に戻って、父の看病をしているのだが、ここは、「先生と私」の部分よりも、興味深い。面白い。ただ、「私」が実家に戻って、家族と接するのは、後半の、先生の過去の話と似たり寄ったりで、先生の方は、親戚に裏切られたという経験が語られ、夏目漱石は、たぶん、それを書きたいのだが、「私」の実家の話でも、微妙に、すごく微妙に、そういうことを書きそうになって、書かないという流れが感じられた。なぜなら、後で先生の手紙の中で、人間の悪について(ここで言うのは財産問題をからめた親戚の変化のこと)書くのだから、ここで、同じことを書いてしまうと、「私」と先生が同一人物みたいな、感じになってしまうから、ここはぐっと押さえて、文体で進めていかなければならない。その感じのほうが、「先生と遺書」のところよりも、面白いとも言える。「遺書」よりも、「両親と私」のところのほうが、現在を進んでいく文体が、美しいし、面白い。「私」の父親が死ぬのを待っている間に、先生から手紙が届いて、「この手紙が届く頃には、私は死んでいるでしょう」というのが目に入って、その手紙が第三章の「先生と遺書」になっているのだが、いくら、先生が死にかけている、あるいは手紙にあるように、もう死んでいるとしても、こちらも死にかけの父を置いて、電車に飛び乗るというのは、あんまり無理があって、笑ってしまった。でもすごく嬉しかった。夏目漱石が、こういう風に書いていることが。昔読んだときは、そんなことにも気付かずに、文体に乗って、前に進んでいったのだが。ここは、どうしても、先生の遺書につなげなければならないから、そして、「遺書」そのものを、作品の第三章に使うために、「私」を先生から離れさせ、離れたところから「遺書」が届かないといけないから、「私」が実家に戻る形になり、そして、就職の口のことで先生の手紙を待っていたのに、ようやく届いた手紙は、就職とは関係のない、分厚い遺書であった、という驚きを創りながら、「私」は目の前のことに集中した日々をできるだけ送って、読者の目をそちらに向けさせ、しかも十分に興味深く読めるように書き込みながら、という風に、夏目漱石になったつもりで、前から順番に読んでいって、ここで「私」の父が死んだらどうなるんだろう、と思い始める。遺書にどう繋げるのか。先生の遺書は、東京に戻ってから読むのだったかな、と記憶を探りながら、「父」が死んでしまうとして、確か先生も死んでしまうはず、死んでばっかりだな、と夏目漱石に憑依したつもりの私が、右往左往しはじめた頃、「私」は父を省みず、電車に乗る。父は、思ったよりもまだ頭がはっきりしているようだった、という説明はあったけれど、電車に乗るのは、ちょっと無理がある。(自然な流れではない)漱石もそんなことには気付いているから、駅で、実家に向けたメモを書いて車夫に頼んだり、頑張ってはいるけど、説得力には欠ける。でもそんなこともおかまいなしに、夏目漱石は筆を進める。その後は先生の遺書の中で、kが死に、父と「私」はもうでてこない。物語としては、破綻しているが、私としては、全然このほうがいい。まとまっているけど、読んでも何も残らないものよりは、破綻も含めて、夏目漱石の生命の流れを感じた気持ちになれるし、物語うんぬんよりも、人間の内部について書こうとしているのだから、この破綻はどうでもいいとも言える。(破綻はしないけど、中身はすかすかの小説が多いから)「先生と遺書」になると、もう書きたいことに焦点を当てているから、まったく淀みはない。この文体の流れは、少しリズムが遅いけど、心地良い。書いている内容も、いい。部屋に上がったときに、kとお嬢さんが、急にお喋りを止めたりするのが、変に気になる先生の感じとか、すごくいやらしい感じが出ていて、面白い。それでも、漱石が書きたいことを書いている、三章よりも、第二章にあたる、「両親と私」のほうが、いい。なぜかわからないが、そのほうが、筆が冴えるな。(冴えるというか、現在を進んでいく二章の感じが、三章の長い語りよりも、小気味良いのかな)いや、三章だって、ドストエフスキーの「地下室の手記」の第一章の語りに似ていて、書いている内容はすごくいいとも思うな。そういう意味では、「地下室の手記」とは構成が逆になっているな、「こころ」は。「こころ」の手紙の文章のトーンは、夏目漱石以後も様々な作家の文章に、見かける。それにしても、人称を省略せず、私、私と書くね。少し、それが気にはなる。でも、一文、一文のリズムから見ると、この繰り返される私が、重要に見えてくる。ここまで人称を省略しない日本語を書くのは、英語を学んだ人に多いのかもしれない。英語では、人称を省略しないからね。よくわかんないけど。この文章の八割を夕方から飯前まで書いたのだけど、これを書いているわたしは、残り二割と思われる部分を書いている今のわたしは、ビールを飲んだ後のわたしです。なので、何書いているか、わからなくなってきました。そういうわけで、これが今のわたしのこころです。ばっはっはー。何だか、何もかも面倒になってきたので、もう寝ます。私は、Kのことを下宿に連れこんでおきながら、今では、抜き差しならない強敵のように思えてきたのです。しかしながら、私はKのことを愛していました。わっはっはー。愛するあまり、愛さなくなったのです。いわば、愛によって、愛が消えていく、こういう逆説の中に、私自身の苦しみ、そして苦しみの中の甘みがあったとも言えます。記憶してください。私は、あなたと会っているときも、いわばKと会っていたに等しいのです。なぜなら、いえ聞いてください。なぜなら、とは書いたものの、なぜなのか、私には分からないのです。それどころか、なぜなら、と書いてから、なぜなのか、私は考えている始末なのです。奥さんは、そんな私に勘付いていましたので、私に作ってくれた弁当のおかずは、Kの弁当とは違って、玉子焼きではなく、目玉焼きでした。私が、これに悩んでいたことを告白しておきます。玉子焼きと目玉焼き。この違いは、私の方をひいきにしてくれたのか、その逆なのか、判断に苦しむものです。この違いに、軍人の妻である奥さんの、何らかの意図があるのではないかと怪しんでいたのです。しかし、これは思い過ごしで、奥さんは、実は私のことを愛していたのです。そのため、私は奥さんと共に山に登りました。そして下山しました。記憶してください。私は、ばかものでした。正直に生きようとして、携帯電話の機種変換をいつまでも遅らせて、解脱気分ではいたが、結局は奥さん好きの、ばかものでした。LOVE。だっはっはっー。だめだこりゃ、という口癖の男がいましたね、これは、Iという男です。正確にはいかりやちょうすけ、という名だったはずです、さらに言うのであれば、これがKの正体なのです。驚かないでください。あなたは真面目なので、最後にあなただけを信じて、これを書いておきます。私は妻を残していきますが、妻はあなたのことが好きなのです。これ以上は言わなくてもわかると思います。ただし、あなたからすると、妻は年増という風に見えるかもしれません。しかし目に見えるものを信じてはいけません。魂は年を取らないのです。その代わり、髭だけは、伸びます。これはホルモンバランスのせいだと科学者は言っていますが、信じてはいけません。なぜなら、とは書きましたが、私は今から、なぜなのか、考えているのです。これは前にも言いましたので、繰り返しましたが、ぜひとも忘れてください。なぜなら、科学者は人間だからです。そして、人間は科学者にもなりうる。科学者が人間で、人間は科学者にもなりうる、という意味ではありません。全ての意味は、無意味なのです。そういうわけで、記憶してください。先生は、自分でいうのもなんですが、先生は、あなたを愛してします。そして妻もあなたを愛しています。そして、奥さんは、私を愛し、Kは実は私と同じ穴のむじなを愛しています。これらは内緒でありますが、愛は結局は、全てに降り注ぐことになります。ですから、あなたがこれを読んでいるときには、私はこの世に存在しないでしょう。とくに死んでいるでしょう。お前はもう死んでいる、という口癖の男の漫画が、いつか始まるかもしれない、と予想しておきます。なぜなら、愛は結局は、全てのものに降り注ぐことになります、そして、この愛からは誰もが逃れられない、いわば業火だと、そのように解釈すればいいというものではありません。それでは、眠ります。おやすみなさい。私は、ビールを飲んで、疲れました。